【1.8MHz用アンテナの建設計画】
<コンテストで使えるアンテナ>
コンテストステーションを作り始めた頃の1.8メガ用のアンテナは、タワーから引き下ろしたインバーテッド゙Vアンテナだった。ARRLの160mコンテストに参加したとき、 いくら呼んでも後回しにされて飛ばないことを痛感し、 ランニング可能なアンテナの建設が始まった。
1.8メガについては当初専用タワー建設の計画が無くて、3.5メガから28メガまでのアンテナを建 てた後には都合の良い場所が残っていなかった。垂直系のアンテナでやることになるので、せめて北方面だけでも良くしたいということで、アンテナエリアの北側部分の急斜面に設置するしかなかった。
<建設の条件>
性能的な条件を考慮しながらも、メンテナンスの手間が掛からないような耐久性と、他のバンドへの影響についても考慮した。さらに工事の安全性の点でも、高所作業で無理をせずに出来るだけ容易に建てられる構造としたい。厳しい要求にも思えるが、いくら性能が良くても完成しないことには使えないし、完成しても期待した性能が得られないことには何の意味も無い。楽をして安心に快適な無線が楽しめるのが一番いい。

【建設の準備】
<アンテナ構造の検討>
既存のタワーを利用してアンテナ製作の手間を省こうと考え、いろいろやってみたが、エレメント構造や取り付け方法、マッチングの方法などの実験はできたものの、実用にはならなかった。この結果を踏まえて設置場所を変え、アルミパイプとパンザマストを組み合わせ、エレベーテッドラジアルの構造で建設することに決めた。約40mのエレメントのうち30mほどをアルミパイプで作り、足りない部分はエレメントの下部にワイヤーで継ぎ足して、下方または横方向に展張する形で、電気的にはシンプルなグランドプレーンを建設することになった。
<3.5メガへの影響状況の実験>
3.5メガ用バーチカルアンテナの近くにアンテナを設置し、影響状況をチェックしてみた。約15m離れて立っているタワーに、1.8メガのエレメントを取り付けたときに、一番近くの3.5メガ用のバーチカルアンテナへの影響をチェックしてみた。エレメントをタワーに取り付けると共振周波数が3.5メガから離れるので影響は感じなかったが、エレメントを外してタワーやマスト部分がたまたま3.5メガに近くなった時には、3.5メガのアンテナSWRが悪化した。近在のタワーなどの影響については、その物が共振していなければSWRなどへの影響は少ないようだ。
<建設場所の整地>
垂直アンテナは周辺の障害物による影響を受けやすいと聞いているので、既存タワーの影響を避けるために北側の隅の僅かな空きスペースに設置することにした。北方向へはラジアルを張るのに苦労しそうだが、北方向はダウンヒルになっていて伝播条件良さそうだ。タワーのステーアンカーのある場所が少し平らになっているが、パンザ建柱の作業性や今後の設備維持を考えてユンボで整地して拡張した。

【アンテナの構造】
<エレメント>
当初、パンザマストにアルミパイプを継ぎ足したフルサイズ構造を検討したが、接地型アンテナは大掛かりなラジアルの設置が必要になるので、高架式ラジアルを採用することになり、アルミパイプ+ワイヤーをパンザマストに絶縁して取り付ける構造になった。アルミパイプで作製するエレメントの先端部分の約5mは14メガのエレメントを流用し、中心部分は既製品の6段式のアルミポールの3本分を組み合わせて製作した。 建設当初はアルミポールをそのまま使ったが、強度が足りず壊れるたびに2重になり3重となった。エレメントとアルミポールだけでは長さが足りないので、80ミリと70ミリの4mパイプを追加し全長を31mとした。さらに、アルミパイプで作ったエレメントの下部に、銅線をつないで不足する分を延長し、全長37m程のフルサイズエレメントとした。ラジアルをエレベーテッド式とするために、16mほどのパンザマストのトップ部分にエレメントを固定し、給電点を地上高を約5mとした。数多くのパイプをつなぐ方法は重ね合わせが強度的に一番いいようだ。突合せをしなければならないときは、内側と外側からサンドイッチ構造にしないと強度不足となることが多いようだ。
<エレメントステー>
自立式で建てる予定だったが、エレメントや支持金具の強度が足りず僅かの風で変形するので、デベロープを使ってステーを取り付けることになった。最初は1段だけのステーだったが、効果が十分でなくてエレメントが曲がる事故の度にステーを2段、3段と増やすことになった。さらにステーの固定位置もドンドン根開きを広げたが、ステーの効きが不足してエレメントの曲り事故が起きるたびにステーの改良が続いた。西側と北側のステーは水平方向の根開きが140度位になっているうえ、山の斜面にあるため垂直の展張角度も30度程度しか取れないので、十分なステー効果が得られないようだ。鋼管柱のステー支持柱を建て、地上から6m位にステーを固定したが、それでも足りないので足場パイプで延長し、約9mほどの高さにステーを固定した。
< ステーの3段化>
2段ステーにしてからしばらくは故障しなかったが、エレメントの先端が折れて落ちてしまったので、エレメントを修復するついでにステーを3段にすることにした。ステーの1段目は元の位置に取り付けたが、2段目はバランスを考えて少し下 げることにした。取付け位置は下から10.5m、18m、25m位の位置に固定した。ステー材料は全部デベロープで、1段目と2段目は5mm、3段目は4mmのデベロープを使った。ステーロープの重みが約3Kgあり、これまでのエレメント構造では工事中にエレメントが傾きいてしまい、架設工事は以前より大分やりにくくなった。
<ステーの取付方法>
デベロープの固定用金具としてグラスファイバー工研から発売されているものは値段が高いので、エレメントに巻きつけて縛り付けていたが、この方法では切れてしまうことがあった。切れた痕跡からステーが風で揺れてステーの根元が折れ曲がるか、エレメントに当たって擦れることがあるらしいので、ステーの取り付け方を改良した。アルミ板でエレメントを挟み込む金具を作り、シャックルなどの金具を使いロープが揺れて接続部に曲げやコスレ現象が起きないように取り付けた。シャックル1個だけで止めてみたが、ロープとエレメントの距離が近いためか再び切れたので、 シャックルにチェーンを切断して作った楕円形のリングを併用して間隔を開けて止めた。その後ステーの切断は無いので効果はあるようだ。ステーバンドの締め付けは十分とは思うが、ずり落ちないようにパイプ接続用のボルトに引っ掛かる場所を選んで取り付けた。シャックルの抜け落ち防止用のバインド線に銅線を使うと、クロメートメッキと電触を起こして錆びるので、被服つきのIV線で縛ることにした。小さいシャックルはプライヤーで締めるだけにした。
<エレメントの支持柱>
24mのアルミパイプを取り付ける支持柱には全長18mのパンザーマスト使った。パンザマストは地上高16mで、根元の太さが65cm、で先端が14cmだった。このパンザマストは開設当時に新井さんから頂いものだがステップボルトは今回新たに購入した。
<エレメント取付金具>
パンザマストにエレメント用のアルミパイプを取り付ける方法は、電柱装着金具のステー取り付けバンドと、Lアングルを使って自作した金具を組み合わせて取り付けた。この方法は3.5MHz用のバーチカルでも経験済みなので強度や使い勝手は 実証済みだ。
<フロートバラン>
バランはいつものように同軸ケーブルをコアーに通した簡単構造のフロート式バランとした。アンテナ自体がアンバランス構造なので、バランは強制バランよりもフロートバランの方が良いらしい。
< マッチングBOX>
エレメントが折れた対策として給電点の高さを低くした時からSWRがうまく下がらなくなったので、コイルとコンデンサーを使ったマッチング回路を取り付けた。

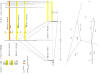


【アンテナの製作など】
<エレメントの組立て>
エレメント材料に使った簡易マスト用のアルミパイプは、両端に接続用のネジ穴が2箇所ずつ開いているので、強度を保つためになるべく既存の穴を使ってパイプを接続した。また、長さを確保するために同じ寸法のパイプをつき合わせてつないだが、既に開いている穴の間隔が20cmしか無く、重ね合わせ部分が短いために強度が不足して折れることもあったので、修復する時は内側と外側に異径のパイプを入れて補強した。エレメント材料の古いものは表面が黒く変色し汚れていたので、サンダーとドリルを使ってきれいに研磨した。エレメントが折れるたびに補強して再建、し最終的にはエレメントの約半分が3重構造となったが、パイプ内部のおくまでは研磨できないので接続部分だけ研磨した。接続部の周囲にはペナトログリースを塗って、10ミリから6ミリのボルトを2本ずつ使って締めた。
<リベットによる接続>
アンテナ修理の時に接続部分を良く観察すると、少しガタがで出ている様子だったので、押さえに打っておいたブラインドリベットを太目のものに交換した。サイズはよく見てなかったが、これまでのものより1ミリほど太いものだった。ハンドツールではなかなか切れず、四転八倒してやっとカシメた。しかし、その後修理の時にリベットの状態を点検したところ、やはり緩みが再発しており強度不足で役に立たたないことが分かったので、 補助固定していた部分以外はボルトナット式タッピングンネジに戻した。
<アルミパイプの重ね合わせ>
エレメント下部の7mくらいの部分を二重化した。この部分は外径80ミリと70ミリのパイプが使われて居り、二重化するには1ミリ程の隙間を空けた二種類のパイプが理想的だが、市販品ではなかなか必要な寸法のものが手に入らないし、値段も高いので、有り合せのアルミパイプを使って間に合わせた。80ミリの部分は内部に65ミリの肉厚3ミリ。70ミリの部分は62ミリと55ミリで肉厚1.5ミリの二重化パイプを差し込んで三重化することにした。重量的には更に15Kgくらい増えて、全体では50Kg位になりそうだ。どちらも隙間がありすぎてガタガタかと思っていたが、特に70ミリのパイプは曲るたびに、何度もその都度押し曲げて修正してきたので、寸法が狂っていて一筋縄では入らなかった。折れない程度にユンボで押し込んだが、どうしても最後までは入らず、予定の長さを30センチほど残して諦めた。
<エレメントの固定金具>
支持柱にエレメントを固定する補助金具を製作した。Uボルトと2枚のLアングルを使い、片側をパンザに取付け、もう片側にエレメントを固定する構造とした。製作はLアングルを切って穴を開けるだけなので、自作するには都合が良いが、厚さ5ミリのLアングルに12ミリの穴を開けるのは結構大変だった。ホームセンターで買えるクロメートメッキのネジは、錆びる心配があるのでインターネットで探したら、大阪に亜鉛どぶ付けメッキのネジを小口販売もしてくれるところがあった注文した。しっかりしたメッキでネジ自体は安いのだが、送料が割高になってしまう。しかし、アンテナ工事にはドブ付けメッキが一番間違いない選択だと思う。
<取付部の絶縁>
エレメント固定部の絶縁は、塩ビパイプを使って絶縁することにした。十分な特性が得られるかどうか不明だが、構造が簡単で入手しやすい材料はこれしか見つからなかった。塩ビパイプはVP-75というサイズのものをホームセンターで購入した。アルミパイプの寸法より小さいので塩ビパイプを切り開いて押し込んだ。1cmほど隙間があり、塩ビの厚みが5ミリ程しかないので、絶縁耐圧が持つかどうかはやって見ないと分からない。
<折れ曲がったエレメントの修復>
下から2段目の直径75ミリのパイプが、接続部分で折れたので修復した。曲ってつぶれてしまった部分は修復不可能だが、そり曲った部分はユンボの廃土板を使って、曲った部分を反対側から押して修復した。注意深く作業すればかなりの精度で修復ができる。 焦って作業するとつぶしてしまう恐れもあるが、慎重にやれば結構まっすぐになり、つぶれた部分を約50センチ程切り取り、元のように重ね合わせてつなぐことができた。上部の細い部分の曲りは、タワーのブラスを押さえにして少しづつ曲げて修正した。
<折れた中間エレメントの修復>
エレメントが1段目のステーから上に2m位の部分で折れた。つなぎ目部分の空ネジ穴からヒビが入り折れていた。接続部分の重ね合わせが短いため二重化の効果があまり無かったようだ。折れた部分を切り取って、中側と外側に40cm位の補助パイプを差し込んだサンドイッチ構造にし、8ミリサイズのステンレスネジを4本使って固定した。接続部分がかなりごっつい感じになるが最も確実な方法だろう。
<エレメント先端部分の修復>
エレメント先端の14ミリパイプねじ穴から亀裂がはいって折れた。折れた部分の長さは6cm位だったので長さの補充はせず、そのままねじ穴を開けなおして固定した。他に部分でもヒビが見えたのでねじ穴の部分を3重にして補強した。固定部の補強目的で使ったリベット止めは、緩むし、穴が大きくなりすぎるので3mmのタッピングビスに戻した。リベット打ちした跡穴は4mmなのでタッピングビスが効くところは5mmのタピングビスで固定しなおした。
<折れて短くなったエレメントの延長>
折れた部分を切り取ったために短くなった分の長さを延長した。一箇所だけで延長するとバランスが悪くなりそうなので、2箇所に分けて半分くらいづつ延長した。保存している残骸の中から、寸法が合うものを現物合わせで探すので、結果的には上部エレメントを殆ど作り直すことになってしまいだいぶ時間が掛かった。
<デベロープの末端処理>
デベロープはコースターを使って、軟銅線を密着巻きして固定した。ワイヤークリップで留めることもても大きな問題は無いが、ネジの締め加減が難しくゆるくて抜けたことがあるし、いくらでも締まるので締めすぎて反って強度が落ちることもあるので厄介だ。応力を分散させて強度を保つために、3本編みにして端を銅線でバインドした。この方法は前回からやっているが抜けることも無 く、バインド線によるロープ被服へのダメージなども無さそうだ。以前はバインド線が緩んですっぽ抜けないようにと、バインド線の上から自己融着テープを巻いたが、黒いダンゴ状態になると、反ってカラスの餌食になるような気がするのでテーピングは止めた。
<フロートバラン製作>
バランの構造はパッチンコアーに同軸ケーブルを通しただけのものだが、コアーの数が少ないようなので、有り合せのもので使えそうなものを追加し、タイラップで止めた。中には特性の分からないものもあったが、無いよりは良いだろうと思う。
同軸ケーブルは10D-2Vでも工作可能だったが、少し細め8D-2W?のジャンク品が手持ちにあったので流用した。コアーを10個位入れると、30センチ程になるので、バラン全体を塩ビパイプに通して、エレメント張り部材と兼用する形にした。塩ビパイプは外形48mmのものを使ったので、取り付けには足場単管用のクランプが使えた。この金具はいろんな形のものがホームセンターで売られているので、パンザマストに止めやすい構造のものを選んだ。バランとエレメントを止める程度の強度としては手軽で簡単な方法だろう。
フロートバランのインダクタンスがどのくらい有るのか測ってみたところ、15μH位しかなかったので手持ちのコアーを適当に付け足した。有りったけのコアーを使ったが、25μHくらいにしかならなかった。これまでのままでも特に不具合が有る訳でもないので取り合え得ず使って見ることにした。
バランの端子板が割れたので、代わりにエレメントクランプを活用した固定具を使い、エレメントとラジアルワイヤーを引っ張り力を支える構造に変更した。また、ラジアルワイヤーをシンプルで止めて、振動によって掛かる曲げ応力の低減を図った。さらに接続用バインド線を2ミリの銅線にしてガッチリと止め、エレメントワイヤーもこれまでの1.6ミリから2ミリに変更した。
ステーの強化対策のあとにも何度かエレメントの反り返り現象がおきていた。風上のステーが弓の弦のような形でエレメントが傾く現象で、ステーを緩めてやるとエレメントは自力で垂直状態に復元する。エレメントに大きな横荷重が掛かるとステーによって垂直方向に引っ張られて、エレメントの弱い部分がたわんでこうなるのだと思 う。しなりが大きくならないようにステーの段数を増やすか、垂直加重を減らすようにステーの根開きを広げる必要があるのだが、これ以上のことは容易にできるものではないだろうと思う。今のところエレメントが損壊せず修復が簡単なために、ステー強化対策はできていない。
<マッチングBOXの製作>
コイルは水道用に売られている直径6ミリの軟銅パイプを使った。コンデンサーはあらかじめ実験して求めた容量に近い固定コンデンサーで代用した。水道用の銅パイプは柔らかいので、空き缶に巻き付けると簡単にコイルが出来上がるが、柔らかいのでしっかり止めないと経年変化があるかも知れない。SWRが下がらないのでマッチング回路が必要になり、いろいろ検討した結果調整が割とやりやすいLCマッチングをやってみることにした。





















【アンテナ架設工事】
<エレメントの引き起こし>
エレメントの立ち上げ作業は、エレメントの下端をパンザマストの根本にロープでしっかり固定し、ワイヤーロープのフックも根本に掛けたまま、下から16m位の位置でワイヤーロープとエレメントを固定し、アンテナ支持柱のトップから引き起こすと、ワイヤーを延ばしたまま引起しと引き上げが出来るので、ウインチの巻取り手間が省けて作業時間の短縮になる。根本部分はしっかり固定してないとずれて大変なことになるので注意が必要だ。風が無ければ殆ど見ているだけで簡単に引き起こせるが、風が有るときはガイドロープを結んでおいて、風に流されないようにコントロールする必要がある。ぶら下がっているステーがパンザのステップや木の根に絡むことがあるので、エレメントのしなり具合に注意しながら作業することが重要だ。
<エレメントの引き上げ>
支持柱に沿って立ち上がったエレメントを支持柱の固定金具まで引き上げ取り付ける。ウインチのワイヤーフックをエレメントの最下部に引っ掛け、緩んでも抜け外れないようにフックの部分はサブロープで捕縛する。エレメントは固定用U金具にゆるく通しておくが、最初は1段目のステーが固定金具より下にあるので、邪魔になら無いように整理して先に通しておくか、ステーが近づいたら一旦U金具を外すなどすることが必要だ。
エレメントを引上げるときは、固定金具にエレメント接続部分のネジが引っ掛かるので、タワートップに昇ってガイドする必要がある。ステーはよく整理して展張する方向を決めておかないと、エレメントに絡み付いて分からなくなるので注意する。木の枝に引っ掛かり苦労するので木の枝打ちが必要だ。
これまでは風が無ければ殆ど真っ直ぐ引き上げられたが、3段目のステーが増えたことにより、引き上げ作業中のエレメントの しなり具合が大きくなり、横加重が増えて固定金具が曲がりそうな状態になったので、途中からはステーを緩く効かせた上体で引上げることにした。作業員が3人入れば1本ずつ持ってコントロールすれば作業性は格段に良くなる。エレメントの引き上げ中はステーがあちこちに引っ掛かるので十分な注意が必要だ。
<ステーの固定>
西側と北側のステーは支持柱に滑車を取り付け、地面からロープを引いて長さを調整できるようにした。滑車に掛かる部分はデベロープでは切れたことがあるのでステンレスワイヤーをつないで強化した。
使い古しのデベロープがあったので、足りない部分は継ぎ足して使ったが、つないだ部分が重くなり振動するのでよくないようだ。当初ステーはブラブラに張っていたが、エレメントの強度アップとともにステーの張り具合を強くして強度アップを図った。
<3段ステーの取付け>
エレメント先端部分の切断対策として3段目のステーを追加したが、支持柱への取付けは手間を省いて2段目のステーと同じ場所に取り付けることにした。ステーが緩んでいるときは良く注意してステーを整理しておかないとステー同士が絡んでしまったり、上下入り組んだりして作業はやりにくかった。デベロープとステンレスワイヤーとの接続部はヒゲが出ていたりして絡みやすいのでキチンと処理しておくと良い。
【ステー断線修理】:20100223
下側のエレメントステーが1本切れていた。この時期は台風並みの季節風が吹いて被害が拡大する恐れがあるので、ARRL-CWコンテスト中に修理をした。修理作業はそれほど難しくはないが、途中までアンテナを下ろさないと手が届かないので厄介な作業だ。約2時間ほどで無事修理を終えて、アンテナは元気になったがオペレートする元気が無くなった。デベロープは外皮が何かに当り擦れるような状態になっていると意外と簡単に切れてしまうようなので注意が必要だ。
【修理のためエレメント取り外し】
下から2段目の直径75ミリのパイプが接続部分で折れて、エレメントの上部が地面に落下したので、修復するために取り外した。地面に落下した部分は手の届くところで接続ネジを外して切り離した。残っていた垂直部分の折れ曲がった部分をパンザトップまですこしずつ下ろした後、エレメント固定金具を取り外した。曲がっていてどのようにはねるか分からないので、固定用金具のボルトを抜いてエレメントの下部にロープを掛けて一旦パンザマストから降りて、 地面でロープを引いて引き外した。外れたときに大きくバウンドしたがワイヤーロープで吊り下がった状態になった。パンザのステップにワイヤーが引っ掛かって、スムーズには下りなかったが何とか地面まで降ろした。







【アンテナ支持柱の建設工事】
<整地作業>
アンテナファームは既にタワーが満杯の状態で、他のアンテナへの影響が懸念されたが、今後とも使用予定が無さそうな北側斜面の下の方に立てることになり、建設予定地の整地作業をした。近くに40mHタワーのステーアンカーがあり、工事のときに一度整地しているので比較的作業はしやすかった。今回はこの部分を拡張する形で、山側を削って谷側へ土を移動し、5~6m四方のスペースが確保した。パンザの脇をユンボが通れるので、タワーのメンテナンスなどの問題はないだろうと思う。
<パンザマスト>
寸法は根元の太さが65cmで先端が14cm。11段で全長で18m。1.5mほど埋めるとして地上の実効長としては16.5m程度になる。以前からファーム内に放置していたため、一番下と2段目のユニットに少し錆が出ていた。この先どのくらいの期間使えるか分からないが、何もしないで建ててしまうよりはいいだろうと、タール系の黒ペンキを塗っておくことにした。
土に埋める部分なので、安くて防錆効果の高いタール系のペンキを塗った。錆びた部分だけ塗ろうと思ったが、1段目は塗っているうちに塗料がダイブ余りそうなので全部塗ることになった。2段目の部材は面倒なので内側の錆びた部分だけ塗った。
ステップボルトが足りないので購入することになった。電柱用のスッテプボルトがあるので使えるかと思ったが、パンザ用はミリネジで電柱用はインチネジなので使えないことが分かり、町の電材店で聞いたが相手にしてもらえなかった。クラブ関係者の中に、関係業者と連絡が取れる人がいて助かった。
<穴掘りと基礎作り>
穴はユンボで掘ると長方形になってしまうが、なるべくパンザマストの寸法に合うように小さく掘った。深くなってくるとユンボのバケットが見えないので注意しながらやったが、少し深くなりすぎたようだ。穴掘りが終わると、底を平らにして石を並べてユンボで押し固め、パンザ専用の底板を入れて大きめの石で四方を固め、合間に小さめのものを挟んで固めた。
<パンザの積み上げ>
基礎部分は2段分を地上でつないで、ユンボで吊り上げて基礎の穴に落とし込んだ。周りを拾ってきた石で囲んで固めた。どれほど効果があるか分からないがコンクリートを使えないので無いよりはマシだろうと思う。水平を取って回りを2/3ほど埋め戻し、コンクリートの”根かせ”を入れて周囲を簡単にならした。余った土 は斜面側に盛り土して整地した部分を補強した。3段目をユンボで吊上げ様子をみたところ、何とか吊り上げられそうなのでやってみた。一人では接合面を合わせるのが大変だったが何とか終わった。
4段目からはボウズを使ってウインチで吊り上げた。ボウズは作業しやすいようにアルミパイプを使ったので、4段目は重さがあり緊張したが何とかクリアーできた。5段目からは段々軽くなって作業しやすくなるが、高くなってくるので、全部一人でやるには準備のための上り下りが大変だった。各段ともにしっかりとつなぎ目を合わせてつないだが、ステップボルトの並びが少しずれているようだ。
<パンザマストの傾き修正>20090405
真っ直ぐ立てたパンザマストも、アンテナを架設し季節風に煽られて、少し東側に傾いてきた。この前はユンボで押して修正したが、ユンボでは押せる方向が限られてしまうので、今日は近くにある桜の木にシメラーを掛けて人力で引いてみた。6ミリのワイヤーしか無くて強度が少し心配だったが、難なく引き起こせた。引きお起こして隙間が開いた根元を棒でつついて埋めたが、このくらいでは固まるまでに再び曲りそうなので、当分ワイヤーを張ったままにしておくことにした。まったく手が掛かるものだ!
【ステー用支持柱】
<ステー効果の改善策>
自立式エレメントでは強度が確保できないのでステーを付けた。ステーの張り方をいろいろ工夫してきたが、ステーの根開き不足を改善するため、北側斜面の林道脇に2本の支柱を立てることにした。支柱は全長8mの鋼管柱だが山の斜面に立てるために、低い場所では支柱トップがやっとパンザの地面と同じになる程度。高い方でも4mほどしか高くならない。バーチカルアンテナの周辺にあまり大きな金属柱は立てたくないのだが仕方ない。
<ステー支持柱の補強>
ステーワイヤーを支える支持柱の筈だが、
急いで立てたので根入れも浅いし、ユンボで掘った穴が大きすぎて、土が固まるまではステーを強く張ると曲ってしまう。このままでは役に立たない。支持柱に支持棒?!が必要そうなので、足場単管を使ってつっかえ棒を取り付けた。支持柱自体がどの程度効果があるかも分からないが、結果を見ながら必要に応じて改善していく予定。
<ステー支持柱の補強追加>
ステーワ

【アンテナの調整】
<共振周波数の確認>
パンザマストのトップに29mパイプエレメントを固定し、エレメントの下部に10mワイヤーを接続してアンテナが出来上がった。SWRアナライザーを使い、給電点でのエレメントの共振点をチェックしてみた。ラジアルがつながっていないので、パンザマストをアース代わりにして測ってみたが、さっぱり分からなかった。しかし、50センチくらいずつ短くしていったら、1mくらい短くしたときにMFJ-259の測定限界の1.7MHzくらいでSWRが 僅かに下がってきた。更に2m位短くした段階ではSWRが2くらいまで下がったが、周波数は以前として1.7MHzのままだった。結局、全長を33mくらいまで短くしても1.79MHzくらいまでしか上がらなかった。測定の間違いではないかとディップメーターでも確認してみたが、同じようにだいぶ低い周波数でかすかなディップが見られる状況だった。MMANAのシミュレートした長さではだいぶ長すぎるようだし、長さだけではなく他に原因がありそうな気がする。
< ラジアルの取付>
エレメント単体での確認を諦めてラジアルをつないで見ることにした。ラジアルの長さは中心周波数1.82MHzの1/4波長の95%となる39.15mとし、敷地内だけで展開可能な南西と北東方向に張った。
<共振周波数とSWRの調整>
給電部に実験用バランとラジアルを取付け、テスト用ケーブルでSWRアナライザーつないでチェックしたところ、SWR値はこれまでとは変わって、1.906MHz付近で1.0になっていた。国内バンドならこれでOKだが、DXバンドの1.82MHz付近まで下げなければならない。1mの銅線を追加しSWRをチェックすると、1.86MHz付近まで下がったが、まだ40KHzほど高いので、更に0.9m程追加したところ、1.84位までしか下がらなかった。
以前3.5で経験したように、ラジアルの張り具合を緩めたところ、簡単に目的の1.82MHz付近にあわせることが出来た。アンテナアナライザでインピーダンスのX値が下がるようエレメントの長さを変えて、共振周波数を1.815MHz付近にあわせた。しかし、この状態ではR値が30オームほどになり、SWRが1.7位あってチョット問題がある。先に共振周波数を合わせた状態で、R値を50オームに追い込むと、共振周波数が100KH以上も下がってしまう事が分かり、エレメントの調整を最初からやり直すことになった。
エレメントを少し短めにしておいて、ラジアルを緩ませると、周波数が下がってインピーダンスが50オームに近づき、マッチングを取ったようにSWRがきれいに落ちるようだ。結果的にはMMANAで計算した長さより、3mほど切り詰めたところで、バンドの上端、下端でSWRが1.3以内に収まった。しかし、共振点が少しずれてしまうためか、リアクタンス成分が少し残るようだ。
< ラジアルによるSWRの変化>
ラジアルの張り方を変えて、SWR値の変動状況を詳しく確認してみた。ラジアルの張り方を変えたときにどのくらい変動するものか詳しいデーターを取ってみた。その結果、ラジアルをピーンと張ったときには、SWR最良点が1870KHz付近まで上がったが、ラジアルを緩めて張ると1780KHz付近まで下がる事が分かった。ほぼ100KHz変動するので、エレメントの長さは現状のままとし、使うときにはSWRを確認して使うこととしたい。
< エレメントが折れてSWRの再調整>
先端から7m位のところで折れて短くなったので、下部のワイヤー部分を延長して再建することになった。このことにより給電点の高さが地上4m位まで下がったせいか、これまでのような方法ではSWR値が1.7位までしか下がらなかったので、マッチングを取る必要が出てきた。Qマッチ、スタブマッチなども検討したが調整が分かりやすくて確実なLCマッチを試してみることにした。

【動作性能など】
<聞こえ具合は?・・・>
<使用感は、、、。?>
【故障の記録】
<エレメントが倒壊>20090211
工事後仮止めしていたステーが抜けてアンテナが倒壊。下から2段目のパイプが折れた。(修復記事は本文中に記す)
<再びエレメント傾く>200902221
期待していた160mのアンテナがまたもや大きく曲ってしまい、使うどころか今にも崩壊しそうな状況になっていた
<三度びエレメントが曲る>20090314
アレコレ対策をしてきたが今のところ決定打のないまま、試行錯誤の繰り返しだ。ステーだけではなくエレメントの強度不足対策も必要になるだろう。
ステーの支柱を立てることにした。エレメント二重化について可能な方法を検討することになった。
< エレメントステーが外れた>20120404
ステー作業中でワイヤークリップが仮止め状態でゆるかった。
<パンザマストが傾いた>20090405
アンテナを架設し季節風に煽られて、少し東側に傾いてきた。
< 4度目のエレメント折れ>20100417
160m用のバーチカルがまた折れてしまった。下側のステーの2m位上の部分で折れたようだが、2段に取ったステーの間で折れている。原因が分からないと対策が難しい。またまた悩みそうだ。
このアンテナはこれまで4回ほど故障し、弱い部分を強化してきた。これまでに強化した部分は再び壊れることは無いので、改良の効果は見えるがまだまだ問題がありそうだ。
< 給電部の改良>20100506
バランの端子板が割れてしまったので、構造を改良して耐久性をアップした。
<エレメントの傾き>20101204
エレメントステーが西風で裏返ってしまうので西側の支持柱の高さをパイプを継ぎ足して延長した。
<ラジアルの断線>20111105
給電部を外して調べて見ると、ラジアルが全部切れていた。
<エレメントが傾いた>20111223
支持柱の傾きやステーロープの固定が緩んで効きが足りないらしい。北側の上側のステーを張り直して復旧した。
<デベロープが切れた>20120410
3方向に2段のステーが南側だけ上下2本とも切れた。強烈な振動による亀裂ではないかと推測し構造を改良した。
<パンザマストの傾き修復>20120419
東に少し傾いていたので近くの木にワイヤーを掛けてシメラーで引いて修復した。
<またもやエレメントが傾いた>20120512
どこかのステーがずっこけて緩んだらしく、またもや160mのアンテナがそり反ってしまった。
<ラジアル線の修理>20121103
ラジアルが地面を這っていて、ビニール線ではイノシシに噛み切られるので、一部だけ古い裸銅線に変えてみた。
<エレメントの傾き発生>20130324
しばらく問題が起きなかったが、先日もかなり強い風が吹いたようで、エレメントが反り返っていた。
<エレメントの先端が折れた>20130622
折れて落ちているのを発見したので折れた時期は不明だが、ネジの部分から折れていた。良く見るとおなじエレメントの反対がもひびが入っているので、ねじ穴の部分を3重にして補強した。リベットで止めていたが緩むし、穴が大きくなりすぎるので3mmのタッピングビスに戻した。
<エレメントの先端が折れた>20130917
台風の影響で再びエレメントの先の方が約7mほど折れてしまった。強風で反り返ることが度々あったので、ステーを3段にしたが、エレメントが細いのでステーを引くとエレメントがたわんでしまいステーの効果があまり無かったようだ。この前上げたときにエレメントが曲がってしまったので、直さなければと思っていたが、直す前に折れて落ちてしまった。何度も繰り返しなので、もう少し知恵を絞った対策をしなければならい。
<エレメントが反り返った>20131017
エレメントの先が7mくらい折れて落ちてしまい、全体の長さが24m位になって強度的にはダイブ強くなったと思ったが、先日の台風26号でまたしてもエレメントが反り返ってしまった。今回は曲がったエレメントが近くにあるCD-78Lに引っ掛かるなどして、これまでの様にステーで弓のように反り返った状態ではなくて、ステーを緩めても自力では元に戻らなかった。反対側からステーを引いて引き起こそうとしたが、CD78に引っ掛かったところが外れなかった。3.8のアンテナの方向に引いたらやっと外れた。いずれにしても台風によってエレメントにかなりの加重が掛かったらしく、かなり下の太い部分が変形していて、エレメントを垂直状態にしても真っ直ぐにはならなかった。
