| 2008 CQ-WW(CW) M2 (on the way) | |||
| バンド | QSO | Zone | Ent. |
| 160m | 36 | 11 | 14 |
| 80m | 238 | 24 | 54 |
| 40m | 1519 | 35 | 108 |
| 20m | 1149 | 31 | 74 |
| 15m | 103 | 20 | 29 |
| 10m | 31 | 9 | 14 |
| 合計 | 3076 | 130 | 293 |
| ポイント | 3,502,017 | ||

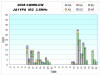
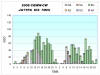
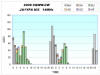

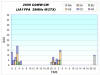
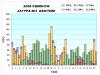
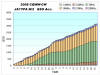
_small.jpg)




<運用状況>
サンスポットが低迷する時期に、さほど多くないメンバーで参加するにはエントリー部門の選択と、オペレータの担当割り当てで結構ややこしい選択が必要になる。
今回は従来よりはだいぶ早めに参加を希望する声が聞かれたことと、設備面でも大きな問題が起きていないことで、幅広い選択が可能なはずだったが、前日になってエントリー部門をM2に決めた。また、運用方法として、これまでは役割分担が決まっていなくて、どれを運用していいのか迷ったり、睡眠をとる時間が中途半端になったりしたことがあった。今回は担当バンドを割り振って、参加者が自分の役割を分かりやすくして、短い期間ではあるが自分の体調管理をしやすくしたつもりだ。オペレーションデスクに張り紙をして担当バンドを表示した。
私とDEA、KEZさんの3人で開始時刻前に現地入りし、準備を済ませてスタートを待った。外回りの準備が済んでシャックに入ると9時近くなると言うのに、7MHzではヨーロッパの信号がガンガン入っていた。とりあえず予定の14MHzと21MHzでランニングを開始。14MHzはソコソコに呼ばれ順調にスタート切ったが、21MHzはちょっと様子がおかしい。
間が少し開いているが、、、、。
土曜日の16時ごろにRCPさんが到着し、早速14Hzのオペレートをチーフオペに交代。スコアーの伸びがグングンとアップし始めた。日曜日は夕方2名のオペレーターが帰宅するとき、車がぬかるみでスリップし、脱出作業のため2時間近くシングルオペ運用になった。若者が帰って中年とロートルが残った。これまで順調に増やしてきたので、最後の追い込みで更なる積み上げをしたいところだ。しかし、土曜日と同じようなコンディションで昼間の14MHzは11時くらいから殆ど聞こえない。早々と夕食を済ませて深夜に備えたが、14がだめなので3.5MHzにでてみた。意外と良く飛んで良く聞こえ、久しぶりに3.5MHzが面白かった。
<コンディションの様子>
14MHzがメインと思われたが、結果的には7MHzの方が開けた時間帯も長く、局数も多かったようだ。7MHzはほとんど途切れることなく開けていたが、ランニングしても14のように沢山は呼ばれない。14Z頃になると14MHzは聞こえなくなり、7MHzのシングルバンド運用になった。土曜日の夜は7MHzのコンディションがよく、局数では14MHzを大きくリードした。
3.5MHzも設備の割には良く飛んで結構楽しめる状態だった。22Z位になってもヨーロッパが開けていたが、M-2TXエントリーのため他のバンドを優先した。また、この時間帯に21MHzでWが少し聞こえだしたが、大きなオープンにはならなかった。
<設備の状況>
3.5MHzのリニアアンプの内部でスパーク。しばらくして再投入したところ自然復旧。恐らくカメムシの仕業と思われる。14MHzのリニアアンプも使用中電源停止。こちらも高圧部品の周辺でカメムシを発見。いずれの原因もカメ虫による一時的な高圧回路のショートと思われる。
昼間の暇な時間帯に1.8MHzのバーチカルにラジアルを2本追加した。しかし、やっと3本になっただけなので気の持ちよう程度の効果しかないだろう。
3.5MHzは送信用が3エレのフェーズドアレーだが、受信用に3.8MHz用の八木アンテナを 使えるようアンテナ切替回路の配線を変更した。最初受信できなかったが、半田付け不良を修理したところ実にすばらしい成果が得られた。
21MHzはリニアアンプ周りの同軸ケーブルの不良が発生し、パワーが出たり出なかったりしたが、コネクターの付け直しで復旧した。
相変わらず、14や7から他のバンドへの高調波の影響がでる。M-2TXなのでM/Mでやるより影響は少ないが、出られる周波数が限られる。
(記:JA1PEJ中村)


_small.jpg)
<ログチェックレポート>
ログチェックレポートがでたので、ログレシーブリストからマルチオペを局をピックアップしてみた。2TX部門に3局。マルチTX部門に3局の参加だった。
いつもの強豪はどちらもマルチOP-Unlimitedなので、2TX部門ではトップらしい。
取敢えず時間ごとの局数が整理できたのでグラフにしてみた。細かいことは分からないが、バンド毎の交信局はおおよそ同じような傾向にあることが分かった。QSOの内容も時間があったら比較してみたい。
得点的には7MHzの方が大きいが、取敢えず14MHzにおける時間当たりのゾーンデーターをグラフ化してみた。生データーのままグラフ化したので、要素が40もあってグラフが見づらく反って分かり難くなってしまった。大陸別に大別した方が分かりやすいグラフになるだろう。大雑把に言えば午後のヨーロッパ方面のデーターに大きな違いがありそうだ。